|
 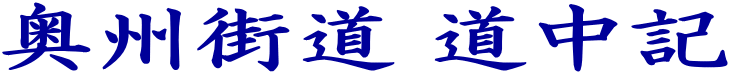 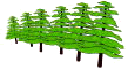
|
白河宿は幕府の道中奉行が管轄する奥州街道の終着地。老中・松平定信の居城であった小峰城の城下町としても発展し賑わった
宿場であった。残念ながら本陣・脇本陣跡などを探すことは出来ないが落ち着いた町並みには往時の面影を感じることができる。 |
  白坂宿を出て「峠道」(左)に差し掛かると雪が一層激しくなってきた。降り止まない雪の峠を越え、国道から右側の集落に入り再び国道に合流。その先の国道289号を横断するころ、ちょっと小降りに。 白坂宿を出て「峠道」(左)に差し掛かると雪が一層激しくなってきた。降り止まない雪の峠を越え、国道から右側の集落に入り再び国道に合流。その先の国道289号を横断するころ、ちょっと小降りに。
7~8分歩くと街道は右に曲がって行くがその角の向こう側に「戊辰の役古戦場跡」(右)がある。奥羽諸藩鎮定に向かった薩長大垣などの西軍と、これを迎え撃つ会津・仙台・棚倉などの東軍が激しく戦った場所。多くの戦死者を弔う石碑が道路の両側に建てられている。 |
  この先は国道とは思えないような狭い道路を道なりに歩き、突き当たりの丁字路を左に曲がる道が奥州街道である。 この先は国道とは思えないような狭い道路を道なりに歩き、突き当たりの丁字路を左に曲がる道が奥州街道である。
丁字路を左に曲がり谷津田川に架かる南湖橋を渡る頃、再び激しい降りとなってきた。橋を渡って数分、雪の向こうに「なまこ壁の土蔵」(左)が。降りしきる雪の中にたたずむ土蔵に思わず1枚。
さらに数分歩くと交差点際に「奈良屋呉服店」(右)の風情ある建物が見える。大正時代の建物だというが雪の向こうガラス戸越しに見える障子が懐かしい。 |
  奈良屋呉服店のちょっと先、交差点の向こうに「月よみの庭」(左)という意味深な公園がある。白河石を敷き詰めただけの公園であるが何故「月よみ」なのか説明が無い。気になる庭だ。 奈良屋呉服店のちょっと先、交差点の向こうに「月よみの庭」(左)という意味深な公園がある。白河石を敷き詰めただけの公園であるが何故「月よみ」なのか説明が無い。気になる庭だ。
公園の一角に「優陽(ゆうひ)の松」(右)という、またまた意味深な赤松が1本。赤松は白河の市民木なのだそうだが説明板に「赤松は西日に当たると若々しく優しい艶を出します」とある。
奥州街道は謎の多い「月よみの庭」の前を右に曲がって行く。 |
  右に曲がり真っ直ぐな道を5~6分歩くと、左、右と曲がる枡形道となる。そのまま枡形道に入るのではなくちょっと寄り道を。 右に曲がり真っ直ぐな道を5~6分歩くと、左、右と曲がる枡形道となる。そのまま枡形道に入るのではなくちょっと寄り道を。
左ではなく右に曲がり「関川寺(かんせんじ)」(左)へ行くと戊辰戦争犠牲者の碑や赤穂義士中村勘助の妻の墓、はたまた何基もの二十三夜塔などが見られる。
関川寺を出て寺の横の路地を入るとその先に「見事な紅葉が」(右)見える。思わずシャッターを押してしまったがここは大きく蛇行した谷津田川畔である。 |
  川畔を上流へ100mほど歩くとなんと「水車小屋」(左)ではないか。この周辺は江戸時代後半から昭和初期にかけて しみず屋、藤屋、米沢屋など多くの精米工場があった場所。その中の1軒、しみず屋の水車を復元したもの。水車がゆっくりゆっくり回っている。 川畔を上流へ100mほど歩くとなんと「水車小屋」(左)ではないか。この周辺は江戸時代後半から昭和初期にかけて しみず屋、藤屋、米沢屋など多くの精米工場があった場所。その中の1軒、しみず屋の水車を復元したもの。水車がゆっくりゆっくり回っている。
その先の妙関寺山門横に樹齢400年の見事なしだれ桜の大木がある。「乙姫桜」(右)と呼ばれているが伊達政宗が将軍家に献木する中の1本を賜ったものだそうだ。 |
  街道に戻り枡形道を抜けて3~4分歩くと白河駅前交差点に出る。街道はここを真っ直ぐ行くのだが右に曲がってちょっと寄り道を。 街道に戻り枡形道を抜けて3~4分歩くと白河駅前交差点に出る。街道はここを真っ直ぐ行くのだが右に曲がってちょっと寄り道を。
「朝によし、昼になほよし晩によし、飯前飯後その間もよし」 と言えば説明も不要だが銚子の袴に徳利と盃は「小原庄助の墓」(左)。大工町の奥、皇徳寺の墓地で見られる。
再び街道に戻り、次の枡形道を抜けて数分の左側、長寿院に「戊辰殉国者墳墓」(右)が設けられている。説明板を読むと戦死者の多くが16歳から20歳という若者であることに胸が痛む。 |
  再び激しくなってきた雪の向こうに見える格子戸の商家は文久3年(1863)創業の「玉家和菓子店」(左)。ちょっと高級な和菓子が並ぶが「白河の四季」という詰め合わせを購入。栗蒸し羊羹が美味い。 再び激しくなってきた雪の向こうに見える格子戸の商家は文久3年(1863)創業の「玉家和菓子店」(左)。ちょっと高級な和菓子が並ぶが「白河の四季」という詰め合わせを購入。栗蒸し羊羹が美味い。
雪も小降りになったので街道へ。玉家菓子店先の信号を左に曲がると そのずーっと先が今回の旅の終着「女石追分」である。
途中に「白河だるま店」(右)が何軒かある。だるまのデザインは かの有名な谷文晁なのだとか。顔には「鶴亀・松竹梅」が描かれているそうだ。 |
  東北線のガードをくぐり、しばらく歩くと田町大橋を渡るが下を流れる川は「阿武隈川」(左)。阿武隈川と言えば 「智恵子抄」 を思い出すが地図を見ると智恵子の生まれた二本松はずっと下流。 東北線のガードをくぐり、しばらく歩くと田町大橋を渡るが下を流れる川は「阿武隈川」(左)。阿武隈川と言えば 「智恵子抄」 を思い出すが地図を見ると智恵子の生まれた二本松はずっと下流。
阿武隈川を渡り坂道を上って行くと右奥に「褜姫(えなひめ)神社」(右)の社がある。この神社には悲しい伝説が。
「時は平家全盛の世。源義経は金売り吉次と共に京都を脱出し藤原秀衡のもとへ。 皆鶴姫も恋しい義経を追ってここまで来たが長旅の疲れで病に倒れ ついに命尽きてしまう。里人が手厚く葬り社を建立した」のだとか。 |
  街道に戻り峠を越すといよいよ追分が近い。道路標示にも「↑会津若松 →郡山」の行き先表示がある。 街道に戻り峠を越すといよいよ追分が近い。道路標示にも「↑会津若松 →郡山」の行き先表示がある。
ついに到着です。幕府管轄の奥州街道終点「女石(おんないし)追分」(右)。しかし、ここには追分道標も説明板も無い。やっと探したのがバス停の「女石」(右)という文字。終わりはちょっとあっけなかった。
街道はこの先「仙台道」を通り「松前道」を通って青森の三厩(みんまや)から海を渡って筥館(函館)まで続く。 |
  日光・奥州街道の旅では戊辰戦争の傷跡が至る所にあったが、ここ追分にも「仙台藩士戊辰戦没之碑」(左)が建てられている。慶応4年(1868)の白河口の戦いで戦死した150余名の慰霊碑である。 日光・奥州街道の旅では戊辰戦争の傷跡が至る所にあったが、ここ追分にも「仙台藩士戊辰戦没之碑」(左)が建てられている。慶応4年(1868)の白河口の戦いで戦死した150余名の慰霊碑である。
奥州街道から追分右側の仙台道をちょっとだけ歩くと戊辰戦争の犠牲者「遊女志げ女の碑」(右)が見られる。
「長州藩参謀の世良修蔵なる人物が一夜、遊女志げ女と遊んだのだがこの地が危険であることを察知して逃走。このことから会津藩士が志げ女を恨み彼女を殺害してしまったのだとか。 |
  雪も止んだので旅の最後にぜひ見たかったのが東北三名城に数えられる「小峰城」(左)。戊辰戦争で落城・焼失したが平成3年(1991)に復元された木造三重櫓の端整な姿が美しい。 雪も止んだので旅の最後にぜひ見たかったのが東北三名城に数えられる「小峰城」(左)。戊辰戦争で落城・焼失したが平成3年(1991)に復元された木造三重櫓の端整な姿が美しい。
小峰城をあとにして向かった駅は「JR白河駅」(右)。大正ロマン漂う駅舎は大正10年(1921)に建てられた木造洋館。かつては「みちのくの玄関口」として賑わったが今はひっそりした駅であった。
奥州街道の旅は「雪の向こうに見る白河宿」という思わぬ良い思い出で締めることができた。 |
前の宿場白坂宿へ 旅の記録へ 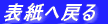
|