|
 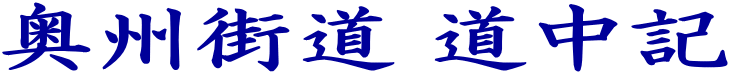 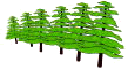
| モー 退屈で退屈でしょうがない。 そんな顔が可愛いんだ |
|
幕府直轄地であった鍋掛宿は最盛期には戸数百余、二十数件の旅籠があったという宿場だが、明治に入ると宿駅制度の廃止と、
鉄道駅から遠かったことなどで急速に賑わいを失い、今は静かな旧宿場街となっている。宿内には江戸時代に建てられたという
芭蕉句碑がある。 |
  山間いの緩やかな坂道を下って来ると「那須塩原市」(左)の標識が目に入る。ついに栃木県の最北まで来てしまったが、さすがにここまで来ると、 うーっ寒い。というのは冗談でして立冬も近いというのに一向に寒くない。今年の天候はどうしたんだろうね。 山間いの緩やかな坂道を下って来ると「那須塩原市」(左)の標識が目に入る。ついに栃木県の最北まで来てしまったが、さすがにここまで来ると、 うーっ寒い。というのは冗談でして立冬も近いというのに一向に寒くない。今年の天候はどうしたんだろうね。
街道沿いには牛舎が結構多い。1軒の牛舎に立ち寄ったら何頭もの牛が一斉にこちらに振り向いてきた。「モー退屈で退屈でしょうがないんだ」(右)、そんな顔がなんとも可愛い。 |
  しばらく歩くと「樋沢神社」(左)という小さな神社があるが、ここに「蹄跡石」(右)と葛籠石と呼ばれる二つの巨石が鎮座している。 しばらく歩くと「樋沢神社」(左)という小さな神社があるが、ここに「蹄跡石」(右)と葛籠石と呼ばれる二つの巨石が鎮座している。
後三年の役(1083~1087)で陸奥平定に向かう八幡太郎義家。戦勝祈願にと丘の上の神社に馬で一気に駆け上がったところ勢いあまって巨石に馬の前足が。このとき石に蹄の跡がくっきり刻まれてしまったのだとか。これが「蹄跡石」(右)。
隣りに「葛籠石」と呼ばれる石があるが、形が葛籠に似ていることから義家が「葛籠石」と命名したと伝えられている。
ともに1000年近く前の言い伝え。 |
  樋沢神社から5~6分歩くと「鍋掛一里塚」(左)があるが、街道際にあるわけではない。見上げるような崖の上。傍らの説明板によると、「鍋掛愛宕峠の塚は道路工事で現在地に移動」とある。かつては「道路工事で撤去」というケースが多かったが復元してくれるとは嬉しいことだ。 樋沢神社から5~6分歩くと「鍋掛一里塚」(左)があるが、街道際にあるわけではない。見上げるような崖の上。傍らの説明板によると、「鍋掛愛宕峠の塚は道路工事で現在地に移動」とある。かつては「道路工事で撤去」というケースが多かったが復元してくれるとは嬉しいことだ。
一里塚の奥、鬱蒼とした杉木立の向こうに見える神社は「鍋掛神社」(右)。深い森に包まれてちょっと寂しげな神社であった。 |
  鍋掛十字路のすぐ先、左側に「清川地蔵」(左)が鎮座している。延宝7年(1679)建立という石仏地蔵だが4月24日の祭礼には集落の全女性が集まり念仏を唱えるのだとか。集落の全女性が集まったらそれはそれは華やかだろうなー。年1回だけとはいえ全女性に囲まれるとは幸せな地蔵様だ。 鍋掛十字路のすぐ先、左側に「清川地蔵」(左)が鎮座している。延宝7年(1679)建立という石仏地蔵だが4月24日の祭礼には集落の全女性が集まり念仏を唱えるのだとか。集落の全女性が集まったらそれはそれは華やかだろうなー。年1回だけとはいえ全女性に囲まれるとは幸せな地蔵様だ。
この辺りから宿場が始まっていたのだが今の「鍋掛の町並み」(右)は人通りも車も少なくひっそりとしている。 |
  清川地蔵の数分先、加茂神社の境内に「芭蕉句碑」(左)が建てられている。この句碑は文化5年(1808)に地元の俳人が建立したもの。 清川地蔵の数分先、加茂神社の境内に「芭蕉句碑」(左)が建てられている。この句碑は文化5年(1808)に地元の俳人が建立したもの。
野を横に 馬牽きむけよ ほととぎす はせを
奥の細道道中の途中、馬子の願いで作った句だそうだ。
数分歩くと正観寺という寺院の山門際に柳?のような大木が。説明板を読むと、なんと樹齢250年の「しだれ桜」(右)であった。 |
  正観寺からさらに数分歩き昭明橋の手前を左に入ると「馬頭観世音」(左)や二十三夜塔などの石塔が見られる。旧奥州街道はこの前を通って川へ下っていたが今は石塔群の先で道が無くなっている。 正観寺からさらに数分歩き昭明橋の手前を左に入ると「馬頭観世音」(左)や二十三夜塔などの石塔が見られる。旧奥州街道はこの前を通って川へ下っていたが今は石塔群の先で道が無くなっている。
元に戻り「那珂川」(右)に架かる昭明橋を渡っていくのだが橋から眺める那珂川は素晴らしい景色。 紅葉していればもっと素晴らしいだろう。
昭明橋を渡ると、すぐに越堀(こえぼり)宿だが街道はさらに山間に入って行く。 |
前の宿場大田原宿へ 次の宿場越堀宿へ 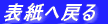
|